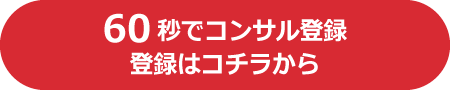RPAとは?日本で多く普及している理由や導入時の効果、注意点を解説

最新更新日:2025/02/14
作成日:2018/02/16
日本でも、急速に導入が進んでいるRPA。
RPAとは、ルーティン業務をロボットに行わせることで、業務効率化を目指すものです。人手不足に対応できる技術として日本でも利用が広がっていて、2022年時点で「日本国内における大企業の約半数がRPAを導入済み」というデータもあります(※)。
一方で年商50億円以下の中小企業の場合、RPAの導入率は12%に留まっており、企業規模によって大きな差がある状況となっています。
これからRPAを導入する場合、「コストに見合う効果が出るかわからない」「社内にRPAを導入できるような人材がいない」といった懸念を持つ経営者の方も多いかもしれません。また、「RPAが流行っているのは日本だけでは?」「他のツールもある中で、これからRPAを導入して時代遅れにならないか?」といった声も聞かれます。
本記事では、日本のRPA事情や事例とあわせ、RPA導入に失敗しないための注意点について解説します。
※出典:【2025年版】RPAの市場規模!急成長の実態と背景を調査|ITトレンド
目次
■RPAとは?
(1)RPAは労働生産性を向上させる
(2)RPAとAIの違いとは?
■RPAの導入によって期待できる効果
(1)人的ミスの削減とコンプライアンス強化
(2)24時間365日の業務対応
(3)コスト削減効果
(4)従業員の働きがい向上
■RPAが流行しているのは日本だけ?
(1)RPAが日本で普及している理由1.少子高齢化による人材不足
(2)RPAが日本で普及している理由2.日本のITリテラシーの低さ
■日本のRPAの市場規模
(1)【2019年】RPAの市場規模
(2)【2020年】RPAの市場規模
■海外のRPAの市場規模
(1)【2023年】海外のRPAの市場規模
(2)【2033年】海外のRPAの市場規模予想
■RPAの導入事例
(1)金融機関に導入されたRPAの導入事例
(2)コールセンターに導入されたRPAの導入事例
(3)大手メーカーに導入されたRPAの導入事例
■RPAは意味がない?失敗しないための注意点
(1)業務のフローやタスクを棚卸しする
(2)RPA導入コストに見合う業務かどうかを判断する
(3)紙を使った業務では、まずデジタル対応が必要
(4)セミナーなどでRPAに関する情報を収集する
(5)社内の理解と協力体制の構築
(6)段階的な導入とPDCAサイクルの実施
■RPAツールの料金相場とは
(1)初期費用
(2)月額費用
(3)保守費用
(4)開発委託費用
(5)研修費用
■RPAツールを選ぶ時のポイント
(1)自社のニーズに適しているか
(2)コストパフォーマンスは適切か
(3)サポートを適切に受けられるか
RPAとは?
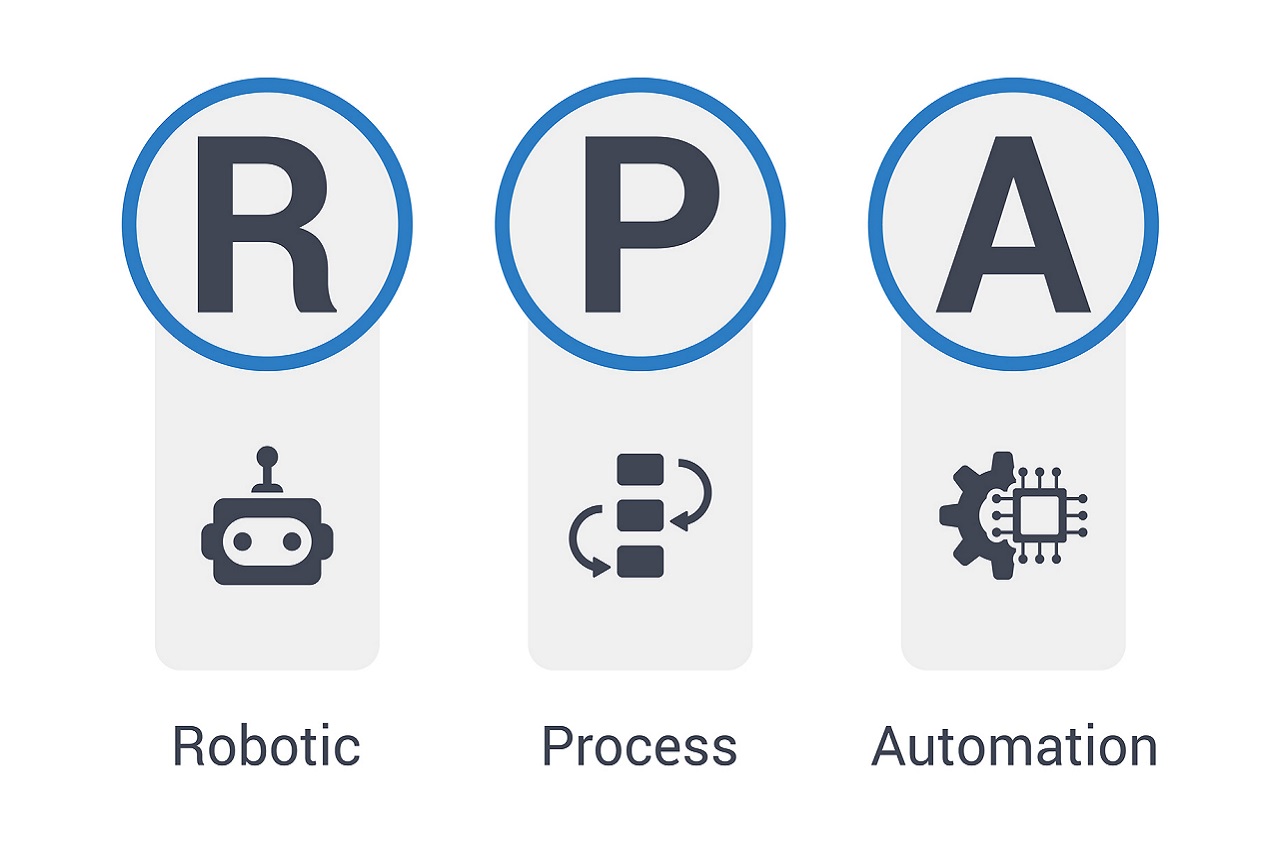
まずは、RPAでできることや、AIとの違いについて解説します。
(1)RPAは労働生産性を向上させる
人手不足を起因とした業務効率化の必要性や、リモートワークなど働き方が多様化する中で注目されているのが、「RPA(Robotic Process Automation)」です。RPAとは、ホワイトカラーと呼ばれる人々が従来人の手で行っていた事務作業を、パソコンやソフトウェア型のロボットが代行する技術のことです。
RPAを活用すれば、人間の作業的な労働時間を削減できます。作業労働時間を短縮できれば、空いた時間をルーティンワークではない、より高度な仕事にあてることが可能です。
労働生産性を上げたい、時間を短縮したいという考えは、意欲的に働いているビジネスパーソンであれば誰もが持っていることです。自動化ツールを使うことで、より高度な仕事に注力しようという試みの一つが、RPAの活用というわけです。
(2)RPAとAIの違いとは?
「RPAとAIは何が違うの?」と感じている人も多いかと思います。AIもさまざまな業務を支援する役立つツールとして注目を集めていますが、AIとRPAには決定的に違う部分があります。
それは、AIは自らの思考を成長させながら我々の業務を支援してくれるツールであるのに対して、RPAの支援方法はあくまで単一的なものであるという点です。
AIは、最初にプログラムを組んだ後も自分で学び続けます。しかし、RPAは最初の制約をあくまで忠実に守ろうとするものであり、決められたルールに対して高い精度を発揮します。
発展性の面で役立つという視点では、AIに軍配が上がるかもしれません。しかし、AIの導入には多大なコストがかかるため、RPAによる支援で十分と考えられるケースも多いのです。同じITを活用した支援であっても、多くの企業にとってRPAはAIよりも現実的な活用方法になりえます。
RPAの導入によって期待できる効果

作業の自動化による生産性向上だけでなく、人的ミスの削減、24時間稼働による処理能力の拡大、コスト削減、従業員の働きがい向上、さらにはデジタルトランスフォーメーションの推進まで、RPAがもたらす効果は多岐にわたります。
(1)人的ミスの削減とコンプライアンス強化
RPAは設定されたルールに従って正確に作業を実行するため、入力ミスやケアレスミスなどの人的エラーを大幅に減らすことが可能です。
定型業務における精度と一貫性が向上し、データの信頼性が高まります。業務の正確性向上は、コンプライアンス要件の厳守にも貢献します。
(2)24時間365日の業務対応
RPAシステムは休むことなく稼働可能なため、夜間や休日でも業務を継続することができます。
データ処理や帳票作成といった時間のかかる作業も、深夜に自動実行するようスケジュール設定が可能です。業務の処理能力と効率性が飛躍的に向上します。
(3)コスト削減効果
RPAの導入は、長期的な視点で人件費の削減につながります。定型業務の自動化により、残業時間の縮減や派遣社員への依存度低下が実現します。
また、業務効率化による生産性向上は、企業の収益性向上に寄与します。
(4)従業員の働きがい向上
単調な繰り返し作業からの解放は、従業員のモチベーション向上をもたらします。
創造的な業務や戦略的な判断を必要とする仕事に注力できる環境が整備され、従業員の成長機会が増加します。職場の活性化と人材育成の促進につながります。
RPAが流行しているのは日本だけ?
世界の中でも、RPA導入に積極的と言われる日本。RPA世界市場の約25%は日本と言われています。一般的なグローバル製品の日本市場比率はおよそ5%~10%となっており、RPAは特に日本の占める比率が高いという見方もできます。
こうした情報から「RPAはすでに海外ではトレンドではなく、人気なのは日本だけでは?」という声も聞かれます。しかし実際には、海外でもRPAは広く利用されています。
RPAツール大手であるアメリカのUiPath社が2023年に行った調査(※)によると、RPAなどのビジネスオートメーションの利用率は、アメリカなど8カ国の中で日本は最下位。日本では業務効率化ツールの利用においては、海外よりも進んでいない状況が浮き彫りになりました。
日本だけが特にRPAの人気が高いわけではなく、世界的にもRPAの導入や利用が進んでいると言えます。
※出典:日本でのビジネスオートメーションの利用率は調査国中で最低、今後の活用に期待
(1)RPAが日本で普及している理由1.少子高齢化による人材不足
日本でRPAが普及している理由のひとつに、少子高齢化による人材不足があげられます。
東京商工会議所と日本商工会議所の調査によると、「人手が不足している」と答えた企業は63.0%であり、そのうち65.5%の企業が「事業継続に支障が出たり、廃業したりする恐れがある」と申告しています。
人材不足を解決するためにRPAを活用し、 効率的・安定的に業務を進める企業が増えているのです。
RPAの導入は、従業員の残業時間の削減にもつながります。従業員の就業満足度や定着率が向上するため、人材不足の解消に有効な手段といえます。
※出典:「人手不足の状況および多様な人材の活躍等に関する調査」調査結果
(2)RPAが日本で普及している理由2.日本のITリテラシーの低さ
日本にRPAが導入されている理由に、海外と比べてITリテラシーが低いこともあげられます。
働く人のITリテラシーが高い海外は、RPA導入の前に、既に業務効率化に取り組んでいる可能性が高いのです。それゆえにRPAの導入に不可欠とされる「業務の標準化」が全社規模で揃っています。
日本はITリテラシーが低い分、社員が業務効率化に取り組むことが少なく、自動化してくれるRPAに頼りたくなるのかもしれません。
日本のRPAの市場規模
普及率に続いて、日本のRPAの市場規模についてまとめました。
(1)【2019年】RPAの市場規模
株式会社矢野経済研究所によると、2019年における日本のRPAの市場規模は、529億円7,000万円というデータが出ています。2018年度は338億円の規模であったため、前年度比56.7%増と推計されています。
(2)【2020年】RPAの市場規模
2020年度のRPAの市場規模は、729億円であると予測されています。前年度と比べると37.6%の伸びが期待されています。成長は継続しているものの、やや減速となる見通しでした。
伸び率がやや減速する理由は、コロナウイルスの影響で、IT投資が抑制されたり顧客との対面機会が激変したりと、事業活動の制限がかかったことだと述べています。
2020年の段階でRPAの導入ブームは過ぎ、今後は本格的な利用拡大に力を入れる段階であるといえます。そのためには、より多くの企業がRPA導入の成功体験を実感することが重要です。
※出典:株式会社矢野経済研究所|RPA市場に関する調査を実施(2020年)
海外のRPAの市場規模
続いてここからは、海外のRPAの市場規模について解説します。
(1)【2023年】海外のRPAの市場規模
カナダやインドを拠点とする企業「PrecedenceResearch」の調査によると、2023年の世界のRPAの市場規模は184億1,000万米ドルというデータが出ています。
世界各地域のRPAの市場規模は、以下の通りです。
- ・アメリカ合衆国:65億3,000万米ドル
- ・ドイツ:16億6,000万米ドル
- ・中国:15億1,000万米ドル
- ・韓国:3億7,000万米ドル
世界のRPAの市場シェア率は北米が39.34%、ヨーロッパが24.86%、アジア太平洋が24.20%とデータが出ています。
(2)【2033年】海外のRPAの市場規模予想
世界のRPAの市場規模は、2033年には1,785億5,000万米ドルに達すると予想されています。2023年のデータと比較すると、10年間で約10倍も伸びていることが分かります。
2033年の予測は、アメリカ単体でも算出されています。2033年のアメリカのRPAの市場規模予想は、548億3,000万米ドルです。
アメリカはロボット導入の発明者や先駆者のひとつとされていて、最も重要な市場といえます。2010年以降、18万台を超えるロボットがアメリカの企業に導入され、120万を超える新しい雇用が作られました。
※出典:
PrecedenceResearch|Robotic Process Automation Market Size, Share, and Trends 2025 to 2034
RPAの導入事例

RPAは、「ロボット」「IoT(Internet of Things)」「人工知能(AI)」といったテクノロジーと並んで、高い関心を集めているもののひとつです。
評価されているポイントは、RPAの導入によって働き方改革や生産性向上の高い効果が期待できるという点。RPAを使って事務作業を自動化することで作業時間を8割短縮できたといった事例もあるように、さまざまな企業にとって役立つ存在になるであろうと期待されています。
(1)金融機関に導入されたRPAの導入事例
RPAは、当初は欧米の金融機関で導入機運が高まったという経緯もあり、日本でも保険会社をはじめとする金融機関で導入が進みました。
たとえば、三菱UFJ銀行では、パイロットプロジェクトとして住宅ローンに関連する保険加入書の点検業務をRPAで自動化。これによって2,500時間の作業時間削減が確認され、本格展開に移行しています。
その三菱UFJ銀行を擁する三菱UFJフィナンシャル・グループとしても、RPAを中心とした自動化やデジタル技術の導入を通じて、オフィスワークの効率化を本格的に促進し、9,500人相当の労働量の削減を目指すとしています。
※出典:
MUFGのRPA導入--2年以上のパイロットから本格利用に移行 - ZDNET Japan
三菱UFJ、自動化で1万人分の労働量削減へ - 日本経済新聞
(2)コールセンターに導入されたRPAの導入事例
コールセンターの受付過程で生じる顧客ステータスの確認や変更作業を、RPAの活用で自動化することによって、処理速度を大幅に向上した導入事例もあります。これまではオペレーター本人、もしくはオペレーターを補助する立場の人間が手動で行っていた作業を、RPAの導入によって大幅に時間短縮できました。
一度の案件で短縮できる時間はわずかかもしれませんが、何百何千という案件をこなしていけば、トータル的に短縮できる時間は莫大なものとなります。RPAの導入によってオペレーターの処遇は確実に変化したと考えられるでしょう。
(3)大手メーカーに導入されたRPAの導入事例
RPAは、食品などを主に扱う大手メーカーでも導入され始めています。今までは情報管理をすべて手作業で行っていましたが、RPAの導入によって情報入力が自動化され、高効率化を実現しているようです。
また、あるメーカーでは卸業者との取引記録にRPAを利用したところ、これまでスタッフが4人がかりで5日かけていた作業がほぼゼロになったとのこと。この作業が毎月行われていたと考えれば、どれだけ多くの時間を他の作業に回せるのでしょうか。あくまでも業種によりますが、RPAが役立つことを実際に証明した一例です。
☆あわせて読みたい
【RPAコンサルタントとは】導入に必要なスキルは?アクセンチュア出身者は有利?失敗しない求人選びのコツを解説!
RPAは意味がない?失敗しないための注意点

RPA導入によってルーティン業務が自動化されるようになると、大幅な労働時間削減が見込めるため、頭脳労働者が本来行うべき仕事に専念しやすくなります。今後は、コンサルタントが企業に労働環境の改善や人材不足の悩みの解消のためにアドバイスをする際、RPAの導入を検討する機会も増えてくるかもしれません。
ただし、やみくもにRPAを導入しても、効果は期待できません。ここでは、RPA導入時におさえておきたい注意点をまとめました。
(1) 業務のフローやタスクを棚卸しする
RPA導入前には一度大掛かり全面的な業務の棚卸をする必要があります。その理由は、主に2つあります。
RPAに向く業務と向かない業務がある
RPAはロボットによる自動化のため、データ入力といったルーティン業務が向いています。また、大量のデータをもとに一定の法則で分析するといった業務もRPAにしやすいでしょう。一方で、定型化されておらず、その都度人による判断が必要な業務となると、RPAには不向きです。
最近では、AIを組み込むことで自動的に判断を行うRPAも登場していますが、その場合もどのようなルールで判断するかを明確にする必要があります。
あらゆる業務をRPAにするという前提ではなく、業務を洗い出したうえで精査し、RPAに向いているかを検討することが大切です。
可視化されていない業務があると、RPA化は難しい
実際には、属人化していて「具体的にどんな作業をしているか担当者しかわからない」という業務も多いのではないでしょうか。
当然ながら、こうした業務があると、RPAの導入は困難です。RPAを導入する前に、全ての業務のタスクとフローを棚卸しして、誰がどんな業務を担っているかを可視化することが必要です。
(2)RPA導入コストに見合う業務かどうかを判断する
業務時間のボリュームがそれほど多くない事務作業。この作業を自動化しても、費用対効果は大きくなりません。
当然ながら、RPAの導入にはコストがかかります。金銭コストでいえば初期費用やランニングコストがかかりますし、RPAが作業を代行できるようにロボットを設定するという労働コストも発生します。
そうしたコストに対して、どのくらいの効果が見込 めるものなのかという点は、あらかじめ検討しておく必要があるでしょう。地方中小企業の場合、導入コストが高額過ぎて割に合わないということも考えられます。
加えて、ロボットの自動化がどの程度可能になるかといった点も確認が必要です。既存のシステムは人が扱う前提で作られていることがほとんどでしょう。
人間であれば何気なく行える操作でも、ひとつひとつの設定が必要なロボットに任せるとなると、意外と時間がかかったり細かい操作のルール化が難しかったりすることもあり得ます。
(3)紙を使った業務では、まずデジタル対応が必要
ビジネスに関するデータがいまだに紙である企業も少なくありません。特に中小企業では、紙が主流というケースも珍しくはないのではないでしょうか。
デジタルデータではなく紙を使った作業が多い業務の場合、RPAが受け取れるようにするには、まずデジタル化の作業が生じます。こうした変換作業には、相当の時間と手間がかかることを認識しておきましょう。
(4)セミナーなどでRPAに関する情報を収集する
RPAがどのようなものなのか、想像しづらいという方も多いかもしれません。こういう場合は、実際に体験してみるのが一番です。全国各地で行われているセミナーでは、ITに関する役立つ情報を聞きながら実際にRPAを体験できるものもあります。
おすすめは、5人~10人程度の小規模セミナー。このくらいの人数ならばセミナー講師から役立つ情報や活用方法などを直接聞きやすいでしょう。講師とのエンゲージメントを図りやすいので、セミナー以降も貴重な情報を確保しやすくなります。
セミナーはRPAの開発や支援を有料で発注してもらうことを目的している場合が多く、セミナー参加費は無料のところもあります。そういったさまざまなセミナーを上手に活用しましょう。
(5)社内の理解と協力体制の構築
RPAの導入には、現場の従業員からの理解と協力が不可欠です。導入の目的や期待される効果を丁寧に説明し、現場の声に耳を傾けることが重要です。現場スタッフは業務の細かいノウハウを持っており、自動化に向けた貴重な助言を提供できる立場にあります。
また、RPAに対する不安や抵抗感を持つ従業員もいるため、雇用への影響や新たな役割についても明確に説明する必要があります。
(6)段階的な導入とPDCAサイクルの実施
一度に多くの業務をRPA化しようとすると、混乱や予期せぬ問題が発生するリスクが高まります。小規模なパイロットプロジェクトから始め、成功事例を積み重ねながら段階的に展開することが賢明です。
導入後も定期的に効果を測定し、必要に応じて改善や見直しを行うPDCAサイクルを確立することが重要です。
RPAツールの料金相場とは
ここからはRPAツールを導入する際に発生する料金相場について、5種類の費用を解説します。
(1)初期費用
RPAツールを導入する場合、一般的に初期費用が発生します。初期費用とは、導入時の事務手続きや環境設定、操作方法の説明などをサポートする費用です。
初期費用の相場は、RPAツールの種類によって大きく異なります。例えば個人のパソコンにインストールする「デスクトップ型」だと、初期費用は無料になるケースもあり、安価になりがちです。
自社サーバーに設置する「サーバー型」であれば、費用は10〜50万円程度とされています。そしてクラウドサーバーで作業する「クラウド型」は、2,000万円程度の高額な費用が発生することがあります。
(2)月額費用
RPAは継続的に使用するツールのため、月額費用が発生します。月額費用はデスクトップ型は5〜10万円、サーバー型は7〜60万円、クラウド型は2〜60万円程度となっています。またツールによっては年間契約になることもあります。
月額費用は利用者数や稼働する数、処理手順などによって異なることがあります。具体的なサポート範囲は、各ツールの提供元を確認してみましょう。
(3)保守費用
RPAツールは作ることがゴールではなく、保守を任せる費用が発生します。
例えばツールが停止した場合の原因調査や、運用手順が明記されたマニュアルの変更などの作業に取り組む必要があります。RPA専門のエンジニアが常駐する場合、1人当たり60〜150万円程度かかります。
保守費用は料金形態によっては月額費用に含まれていることがあるので、詳細を確認してみましょう。また社内にトラブル対応に強いエンジニアがいれば外注費用はかかりません。
(4)開発委託費用
開発委託費用として、RPAのシナリオ作成やロボットの開発を委託する費用がかかります。ツールによっては比較的簡単に開発できる一方で、高度なRPAを開発する場合、外部のRPAエンジニアに委託する方が後のエラー発生頻度が低くなります。
費用はロボット1体に対して15〜30万円程度かかるとされています。
(5)研修費用
RPA導入時に研修費用がかかります。研修を行いRPA管理者を育成すれば、RPAエンジニアの常駐が不要となり、高額な保守費用がかかりません。社内でRPA活用が広がり、企業にも良い影響をもたらします。
研修は数時間または数日間で学ぶ内容が多く、費用は1人当たり3〜30万円程度かかるとされています。
RPAツールを選ぶ時のポイント
ここからはRPAツールを選ぶ時のポイントを解説します。ツールを決める前にぜひご一読ください。
(1)自社のニーズに適しているか
自社で求める機能が付いているのか、きちんと確認することが大切です。選択するRPAツールによって、何ができるのかが異なるからです。まずは、自社のどのような課題を解決したいのかを明確にしましょう。
企業の課題は、例えば「人的ミスを減らしたい」「ルーティンワークを自動化したい」などがあげられます。RPA導入の目的を明確にした後に、RPAツールを選ぶと失敗しにくくなります。
無料キャンペーンを実施しているツールもあるので、実際に使って見ると良いでしょう。
(2)コストパフォーマンスは適切か
RPAツールのコストパフォーマンスが適切か、事前に確認することが大切です。例え予算が限られていても、価格の安さだけで決めてしまうのは危険です。
機能が足りないと企業の課題解決に至らず、目的を果たせないことになりかねません。つまり、予算と機能とのバランスを社内で練ることが重要となります。
余計な機能がたくさん付いているツールは、コストを無駄にしてしまう可能性があります。複数のツールの機能を比較し、どれが自社に合っているのかを検討しましょう。
(3)サポートを適切に受けられるか
トラブルが発生した時やメンテナンスを要する時に、サポート体制が万全なのかを確認することも大切です。トラブルが解決しないと、あらゆる業務が滞ってしまう恐れがあるからです。
自力でトラブル対応ができるか心配である場合、手厚いサポートがあるツールを選ぶとスムーズです。メールやチャット以外にも電話対応が可能であれば、具体的・効率的に解決に向かうことができます。
ただし、サポート体制が充実するほど、費用は高額になる傾向にあることを把握しておきましょう。
RPA導入によって、柔軟な働き方を実現できる可能性も

2019年からスタートした「働き方改革」。人手不足が深刻化する中、あらゆる企業が長時間労働を減らし、多様な働き方を受け入れる働き方改革が求められています。
コロナ禍以降はさまざまな観点からリモートワークの導入も珍しくなくなりましたが、RPA導入によってさらにリモートワークを促進できるという効果にも、注目が集まっています。
一方でセキュリティ上の理由などで、リモートワークで対応できない業務もあります。こうした業務をRPAによって自動化できれば、出社を余儀なくされていた社員もリモートワークが可能になります。つまりRPAによってさらに柔軟な働き方が促進され、労働環境の改善につながる効果が期待できるというわけです。
柔軟な働き方の推進は社員側のメリットだけではありません。企業にとっても「子育てや介護を担う社員の離職防止策になる」「人材の居住地にこだわらず、幅広く採用できる」といったメリットもあります。
RPAの将来性と発展の方向性
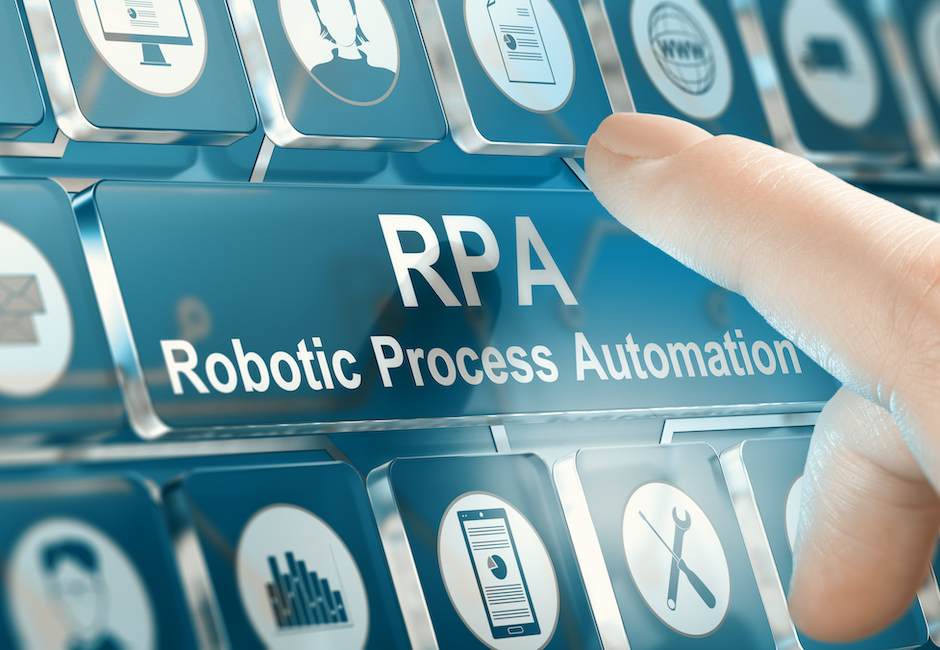
RPAは今後、AIやOCR(光学文字認識)などの技術との統合がさらに進むと予想されています。特に注目を集めているのが、いわゆる「インテリジェントオートメーション」の実現です。RPAの自動化能力とAIの判断能力を組み合わせることで、より複雑な業務への対応が可能となります。
近年では、ローコード・ノーコードのRPAツールが急速に普及しています。プログラミングの専門知識がなくても、業務担当者自身が自動化を実装できる環境が整いつつあります。結果として、多様な業務分野での活用機会が広がっています。
まとめ
ルーティン業務をロボットによって自動化させ、業務効率化やコスト削減が見込めるRPA。従来ルーティン業務を担っていた時間をより高度な業務に回すことができるため、生産性を上げて売上アップにつながる効果も期待できます。
海外でもRPA導入は進んでいますが、特に人手不足が深刻となっている日本では、今後もRPAへのニーズは高い状態が続くでしょう。大企業だけではなく、中小企業にも広がることが予想されます。
ただしRPAを導入して効果を上げるには、日本企業に多く見られる「紙に依存している」「属人化している業務が多い」といった課題をクリアにしなければなりません。そのためにも業務の棚卸をしっかり行った上で、どの業務にどのようなシステムを採用すべきかを判断する必要があります。
RPA導入で失敗しないためには、準備段階から専門家に協力を仰ぎ、プロジェクトを推進するとよいでしょう。
→→転職を検討中の方はコンサルネクストで無料登録
→→フリーランスの方はこちらからコンサル登録
(株式会社みらいワークス FreeConsultant.jp編集部)
◇こちらの記事もおすすめです◇
「RPAエンジニアの将来性とは?フリーランスや副業で稼げるのか」